車枠応力測定試験(ひずみ測定試験)
モノコックボディ車枠応力測定試験・梯子型フレーム車枠応力測定試験

ボディカットやボディ延長の改造時に必要な試験となります。基本的にモノコックボディの試験となりますが、複雑な構造のフレーム車にも対応します。応力がかかる部位にひずみゲージを取り付け実走し、車体のねじれ等を測定します。試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。
ドアラッチ及び扉保持装置強度
協定規則第11号

主にキャンピングカーに使用される扉のラッチ及びヒンジの強度試験を行います。扉の設置場所(側面または後面)により試験内容が異なります。試験内容は国際基準である協定規則に沿って行い安全性を確認いたします。試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。
座席ベルト取付位置
協定規則第14号5.

国際基準であるECE Regulations No.14への適合性を確認する作業となります。シートベルトの取り付け位置を変更した場合などに必要となり、座席ベルト取付強度試験と合わせてご依頼いただくことが多い項目です。適合性確認書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。(対象:M、Nカテゴリ)
座席ベルト取付強度
協定規則第14号6.

国際基準であるECE Regulations No.14への適合性を確認する試験となります。シートベルト取り付け部を変更した場合などに必要となります。取り付け部分の形状により、強度検討と強度試験のいずれかにて適合性を確認します。座席ベルト取付位置と合わせてご依頼いただくことが多い項目です。試験成績書・強度検討書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。(対象:M、Nカテゴリ)
座席背もたれ及びその調節システムの強度試験
協定規則第17号6.2.

国際基準であるECE Regulations No.17への適合性を確認する作業となります。座席を交換した場合等に必要となります。また、当該座席より後部にも座席がある場合には試験項目が増えます(背面の衝突安全性)。試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。(対象:Mカテゴリ)
座席取付装置、調節、ロックシステム及び移動システムの強度試験
協定規則第17号6.3.

シートレールの強度試験となります。回転式等の特殊機構シートレールや座席交換に伴うシートレールの変更、座席新設時に必要な試験となります。試験内容は協定規則に沿って行われますので試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。(対象:Mカテゴリ)
頭部後傾抑止装置の性能試験
協定規則第17号6.4.

座席の交換・新設を行った場合に必要(運転者席と並列の外側座席は必須)となり、前2項と合わせた試験となります。シートに取り付けられている分離型ヘッドレストまたは座席一体型ヘッドレストに対して適度な柔軟性があるかを確認する試験となります。試験内容は協定規則に沿って行われますので試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。(対象:Mカテゴリ)
座席背もたれ及び頭部後傾抑止装置のエネルギー散逸を調べる試験
協定規則第17号6.8.

座席の交換・新設を行った場合に必要(最後部座席を除く)となります。シート背面またはヘッドレスト背面に対して衝撃吸収能力があるかを確認する試験となります。試験内容は協定規則に沿って行われますので試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。(対象:Mカテゴリ)
荷物移動時の乗員保護に関する特別要件
協定規則第17号5.16.

座席の交換・新設を行った場合に必要(座席後部に手荷物を積載する場所のない座席を除く)となりなります。シート構造全体に対して手荷物を模した試験材を衝突させ強度があるかを確認する試験となります。試験内容は協定規則に沿って行われますので試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。(対象:Mカテゴリ)
難燃性試験
別添27 内装材料の難燃性の技術基準
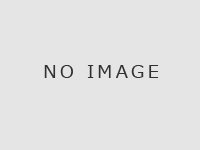
車両の内装材、座席素材などの難燃性確認試験となります。生地単体での試験も可能です。専門機関へ代行依頼する試験となり、試験成績書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。
ガソリンエンジン排気ガス測定
任意測定

ガソリンエンジンのマフラーから排出されるガス濃度を測定します。CO及びHCの測定が可能で、継続検査前のアイドリング調整にご利用いただけます。また、必要に応じて空燃比計等を取り付けレース車両等の燃料噴射量調整などのセッティングも受託しております。
騒音測定(近接・定常)
任意測定
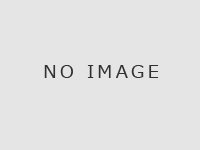
技術基準に沿った測定方法で、検査前の確認や製品開発の参考値としてご利用いただけます。
車両重量測定
任意測定・各軸及び各輪重量

レース用として使用されている海外メーカー製のウエイトゲージを使用して軸重及び輪荷重を測定致します。一般的なゲージよりも高荷重に対応しておりライトトレーラー等の軽量車からフルサイズのキャンピングカーまで測定することが可能です。各種届出時、強度検討時には車両重量の測定が必要不可欠です。
最大安定傾斜角度測定試験
任意測定
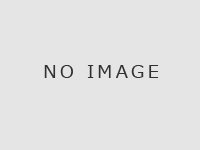
車両寸法や重量により、実測・計算などで最大安定傾斜角度を算出します。試験成績書・計算書はそのまま車両登録時に陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。
被牽引車制動装置
別添15 3.5.
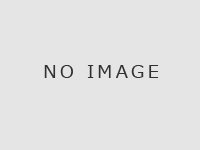
トレーラーの駐車ブレーキに関する別添15 3.5.の適合性の確認試験です。車両をお預かりしての試験となりますが、場合によっては出張試験も可能になります。また、車両構造によっては能力計算により対応が可能な場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。試験成績書・計算書はそのまま陸運局・自動車検査法人・軽自動車検査協会に提出することが可能です。
制動装置技術基準適合試験(代行)
別添10 トラック及びバスの制動装置の技術基準・別添12 乗用車の制動装置の技術基準

公的機関で行われる制動試験です。試験機関との打ち合わせや日程調整をはじめ、試験場への車両搬出入、試験場での立ち合いまでフルサポートしております。万一、基準を満たさなかった場合でも改善策のご提案を行います。試験は予約から実施まで3ヶ月~半年を要しますので、余裕をもってご相談ください。
ブレーキアシストシステム(BAS)試験
協定規則第139号ブレーキアシストシステム(BAS)
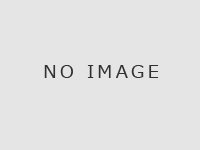
ブレーキアシストシステムのM1カテゴリ適合確認試験となります。大量のデータが必要になるため、試験機材設置から試験実施までにはある程度の日数がかかりますので、余裕をもってご依頼ください。
操縦装置試験
協定規則第79号操縦装置
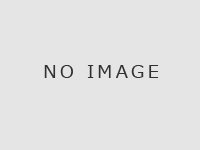
カテゴリ変更での登録時に必要になる場合があります。試験コースが特殊なためコース予約に1か月以上かかります。時間的余裕をもってご依頼ください。
排出ガス測定試験(代行)
別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法

指定機関で行われる排ガス試験です。試験機関との打ち合わせや日程調整をはじめ、試験場への車両搬出入、試験場での立ち合いまでフルサポートしております。万一、基準を満たさなかった場合でも改善策のご提案を行います。試験は予約から実施まで2週間~1ヶ月を要しますので、余裕をもってご相談ください。